大阪大学の漢方研究
大阪大学は、その源流をたどると、緒方洪庵の適塾にさかのぼることは、誰もが知る有名な事実である。現在も、免疫フロンティアセンター(IFREC)のような世界トップレベル研究拠点を有し、日本における医学研究の中心地のひとつである。漢方医学とは遠くかけ離れている印象でありながら、興味深いことに、その歴史をひも解くと、大阪大学が、漢方医学の発展に大きく貢献していることがうかがわれる。やや忘れられた感のある偉大な先人の足跡を訪ねる。山村 雄一(やまむら ゆういち)1918-1990
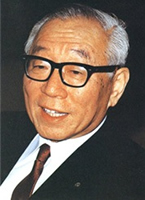 山村雄一先生は、第十一代大阪大学総長を務め、大阪大学を現在のような、免疫学、分子生物学の中心地となるよう奔走され、IL-6の発見者である岸本忠三・平野俊夫先生を初めとする多くの優秀な人材を育て上げ、その功績から、大阪大学の「中興の祖」と称されている。その偉大な足跡は、すでに多くの方が記されているので、ここでは割愛させていただくが、その幅広い研究領域のなかには、意外なことに漢方医学も含まれていた。
山村雄一先生は、第十一代大阪大学総長を務め、大阪大学を現在のような、免疫学、分子生物学の中心地となるよう奔走され、IL-6の発見者である岸本忠三・平野俊夫先生を初めとする多くの優秀な人材を育て上げ、その功績から、大阪大学の「中興の祖」と称されている。その偉大な足跡は、すでに多くの方が記されているので、ここでは割愛させていただくが、その幅広い研究領域のなかには、意外なことに漢方医学も含まれていた。現在の和漢医薬学会につながる和漢薬シンポジウムを1967年に立ち上げられ、和漢薬研究所(現在の富山大学和漢医薬学総合研究所)の設立にも尽力された。富山で行われた第一回のシンポジウムの参加者をみると、漢方側から浅田流を引き継ぐ細野史郎先生、北里東洋医学研究所二代目所長の矢数道明先生、薬学からは木村正康先生(後の和漢薬研究所教授)、大浦彦吉先生(和漢薬研究所教授、後の所長)などが参加され、各界の重鎮がまさに一堂に会している印象がある。その他にも、近畿大学東洋医学研究所の設立にも関わられ、初代所長として有地滋先生を送られている。漢方研究の人材についても、九州大学生化学教室時代の弟子であり薬用人参の研究をされた大浦彦吉先生、大阪大学第三内科での弟子である熊谷朗先生、矢野三郎先生、山本昌弘先生など多彩な人材を育てられた。また、北里東洋医学研究所の三代目所長である大塚恭男先生とも、漢方研究の交流をすすめられ、「最新の漢方薬理 : 漢方薬の科学的な検証と展望」(細谷英吉・山村雄一監修/大塚恭男・熊谷朗・高木博司編集1988年 Excepta Medica)などの著書も出版されている。
山村先生は、漢方研究においては、主にオーガナイザーとしての役割を果たされたのであるが、漢方医学に対する理解も深かったことが伺われる。「最新の漢方薬理1988」に書かれた「漢方医学の現状と将来の展望」の内容を少し取り上げてみたい。
「西洋医学においては病態を明らかにし、病気の原因を解明すれば、まず第一に病因を取り除くことを試み、さらに病態を正常に速やかに回復させる努力をする。今世紀の半ばくらいまでは、病理解剖学や病理組織学が病因と病態の解明に主役を演じてきたのであるが、最近の40年間に、めざましい進歩と発展を遂げた動的生化学、分子生物学(分子遺伝学)、免疫学などのインパクトを受けて、西洋臨床医学はすっかり変貌したといってよい。」といわゆる西洋医学が変革した状況を説明され、次にその状況下での漢方医学の適応についての考察を述べられている。「漢方医学の特徴を基に、その薬効を発揮する病態を考えると、むしろ臓器、組織を横断的につなぐ疾患を対象とするほうが当を得たものとなるであろう。たとえば、内分泌と代謝の異常、免疫の異常、慢性化した炎症などであって、さらに慢性かつ全身に影響を与えながら進行する癌や慢性感染症などもあげられるであろう。~中略~すなわち、漢方医学の対象は「病態」の改善であって「病因」の除去ではないということである。」と現在でも示唆に富む指摘をされており、その慧眼に驚くばかりである。他にも、「証」の近代的解釈とその意義の確立、「方」の薬効の客観的評価や新しい適応症の開発などの必要性を挙げられている。また、その後の小柴胡湯による間質性肺炎の問題が起こる以前に、漢方の長期使用における副作用に対する注意喚起をされている。 この総説から現在にいたるまでに、サイトカインの発見、抗体医薬の開発、ヒトゲノムの解読、プロテオミックス、ゲノミックスなどの網羅解析技術やバイオイメージング技術の進歩など、生物科学を取り巻く環境は、目まぐるしく変化している。現在になって、ようやく山村先生が考えられたことが検証できる時代が訪れたようにも感じられる。偉大な先人が示された方向性は、漢方研究に関わるものが忘れてはいけないものではないだろうか。
熊谷 朗(くまがい あきら) 1920-2009
 熊谷朗先生は、1945年岡山大学卒業後、大阪大学第三内科に入局し、内分泌グループを立ち上げ、山村先生のもと、助教授をつとめられた後に、千葉大学第二内科教授、富山医科薬科大学(現在富山大学医学部)副学長、病院長などを務められ、日本アレルギー学会、日本内分泌学会、日本動脈硬化学会、日本臨床代謝学会などの会長を歴任され、日本のアレルギー学、内分泌代謝学を牽引された方である。
熊谷朗先生は、1945年岡山大学卒業後、大阪大学第三内科に入局し、内分泌グループを立ち上げ、山村先生のもと、助教授をつとめられた後に、千葉大学第二内科教授、富山医科薬科大学(現在富山大学医学部)副学長、病院長などを務められ、日本アレルギー学会、日本内分泌学会、日本動脈硬化学会、日本臨床代謝学会などの会長を歴任され、日本のアレルギー学、内分泌代謝学を牽引された方である。熊谷先生と漢方研究の関わりは、大阪大学時代にミノファゲン製薬に甘草エキスの電解質ホルモン用作用の機序の解明を依頼されたことから始まっている。ステロイドホルモンが非活性化される肝臓において、非活性化酵素をグリチルリチンが阻害するのではと考え、1957年にグリチルリチンが4Δ-steroid reductaseの強力な阻害作用があることを弟子の矢野三郎先生(1928-2006 後の富山医科薬科大学第一内科教授)とともに発見した。千葉大学時代にもその研究は続けられ、最終的に、グリチルリチンが11β-hydroxy steroid dehydrogenaseを阻害し、ステロイド非活性酵素の抑制によってステロイド作用があらわれ、ひいては、抗炎症、抗アレルギー、ステロイド増強作用があらわすことを明らかにした(「私と和漢薬 熊谷朗」現代東洋医学1991 参照)。ちなみに、グリチルリチンの作用活性部位がアグリコンであるグリチルレチン酸であることは、矢野三郎先生によって明らかにされた。千葉大学時代には、山本昌弘先生(千葉大学助教授、日生病院名誉院長)とともに薬用人参や柴胡の有効成分と薬理作用を解析された。 熊谷朗先生は、温厚なお人柄であり、学会活動においても重要な役割を果たされた。第一回から和漢薬シンポジウムに参加し、その運営に携わられ、1985年シンポジウムが和漢医薬学会としてリニューアルされたときには、第一回会長を務められている。第四回には、その功績をたたえられ学会賞も受賞されている。その他には、2012年に第37回を迎えている千葉東洋医学シンポジウム発足にも尽力された。熊谷先生は、山村先生の理念のもと、漢方研究を推進された立役者である。甘草による偽性アルドステロン症、現在では、医療関係者でなくても知られている現象であるが、その解明に大きく貢献された先生の功績も心にとめておいて頂きたいものである。
高橋 真太郎(たかはし しんたろう) 1909-1970
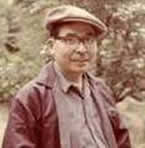 京都薬専(現京都薬科大)卒業。東京帝大で朝比奈泰彦教授の指導をうけ、当時、大阪大学薬学部教授であった木村康一先生(後に京都大学薬学部教授、初代和漢薬研究所所長)のもと助教授をつとめられ、後に教授に就任された。在任中に病床に就かれ、惜しまれつつも永眠。高橋先生は、薬学史に精通され、本草書の研究から生薬の研究を行われた。特筆すべきは、附子の無毒化の研究である。簡便で安定した減毒法としてオートクレーブによる加熱処理を考案され、三和生薬が特許権を取得し販売となった。特許権の切れた現在では、いわゆる加工附子としてツムラも販売をおこなっている。その他にも、大黄や朮の研究を行われた。漢方生薬のエキス化にあたっても、当時助手であった桑野重昭を小太郎生薬生理化学研究所に所長として送り込み、開発を支援された。
弟子としては、植物学的にトリカブトの成分研究を比較検討された難波恒雄先生(大阪大学講師、後に富山大学薬学部教授、和漢薬研究所所長)、正倉院宝物の蘭奢待を分析調査され、医学史にも精通されている米田該典先生(大阪大学薬学部助教授、現在大阪大学医学史料室)などがあげられる。
京都薬専(現京都薬科大)卒業。東京帝大で朝比奈泰彦教授の指導をうけ、当時、大阪大学薬学部教授であった木村康一先生(後に京都大学薬学部教授、初代和漢薬研究所所長)のもと助教授をつとめられ、後に教授に就任された。在任中に病床に就かれ、惜しまれつつも永眠。高橋先生は、薬学史に精通され、本草書の研究から生薬の研究を行われた。特筆すべきは、附子の無毒化の研究である。簡便で安定した減毒法としてオートクレーブによる加熱処理を考案され、三和生薬が特許権を取得し販売となった。特許権の切れた現在では、いわゆる加工附子としてツムラも販売をおこなっている。その他にも、大黄や朮の研究を行われた。漢方生薬のエキス化にあたっても、当時助手であった桑野重昭を小太郎生薬生理化学研究所に所長として送り込み、開発を支援された。
弟子としては、植物学的にトリカブトの成分研究を比較検討された難波恒雄先生(大阪大学講師、後に富山大学薬学部教授、和漢薬研究所所長)、正倉院宝物の蘭奢待を分析調査され、医学史にも精通されている米田該典先生(大阪大学薬学部助教授、現在大阪大学医学史料室)などがあげられる。山本 昌弘(やまもと まさひろ) 1933-
 山本昌弘先生は1959年大阪大学医学部卒業後、大阪大学第三内科に入局し、ステロイドホルモンの研究で学位を取られたのちに、アメリカへ留学し、1968年第三内科助手となったときから和漢薬の基礎・臨床研究を始められ、第三回和漢医薬シンポジウムから参加をされている。熊谷先生のもと千葉大学第二内科にて講師、助教授をつとめられ、内分泌代謝・糖尿病・動脈硬化・和漢薬グループの創設に従事された。1979年日生病院内科部長、1990年同、院長に就任され、2002年より名誉院長となり、現在に至っている。
山本先生は、人参サポニンやサポニン成分であるジンセノサイドがラットの骨髄細胞の生合成増加・細胞増殖作用を有することを発見され、薬用人参の薬効を生化学的に世界で初めて証明された。高脂血症モデルラットにおいて、柴胡サポニンA,D、ジンセノサイドがコレステロール低下作用を有することを示した。肝障害モデルラットにおいて、ジンセノサイドや柴胡サポニンの抗炎症作用と代謝作用についても解析されている。さらに、ラットによるモデル研究にとどまらず、薬用人参の臨床研究や慢性肝炎における小柴胡湯の臨床データーなどを示された。その功績をたたえられ、第十二回和漢医薬学会賞も受賞されている。
山本昌弘先生は1959年大阪大学医学部卒業後、大阪大学第三内科に入局し、ステロイドホルモンの研究で学位を取られたのちに、アメリカへ留学し、1968年第三内科助手となったときから和漢薬の基礎・臨床研究を始められ、第三回和漢医薬シンポジウムから参加をされている。熊谷先生のもと千葉大学第二内科にて講師、助教授をつとめられ、内分泌代謝・糖尿病・動脈硬化・和漢薬グループの創設に従事された。1979年日生病院内科部長、1990年同、院長に就任され、2002年より名誉院長となり、現在に至っている。
山本先生は、人参サポニンやサポニン成分であるジンセノサイドがラットの骨髄細胞の生合成増加・細胞増殖作用を有することを発見され、薬用人参の薬効を生化学的に世界で初めて証明された。高脂血症モデルラットにおいて、柴胡サポニンA,D、ジンセノサイドがコレステロール低下作用を有することを示した。肝障害モデルラットにおいて、ジンセノサイドや柴胡サポニンの抗炎症作用と代謝作用についても解析されている。さらに、ラットによるモデル研究にとどまらず、薬用人参の臨床研究や慢性肝炎における小柴胡湯の臨床データーなどを示された。その功績をたたえられ、第十二回和漢医薬学会賞も受賞されている。
※当サイトで掲載されている写真・イラスト及び記事等の無断転載を禁止します

